数ある野菜の中でも赤・黄色・オレンジと色鮮やかな「パプリカ」。
甘みがあり食べやすいので、ピーマンは苦手でもパプリカなら食べられるという方も多いのではないでしょうか?
そんなパプリカですが、同じパプリカでも赤・黄色・オレンジ、それぞれの色によって含まれる栄養素にも違いがあります。
パプリカの色素成分の違いによるものが主な栄養素の違いになっているのですが、パプリカの中でもビタミンが豊富と言われる「赤パプリカ」。
「赤パプリカ」にはビタミンA・C・Eが含まれていて、このビタミンA・C・E(ビタミンエースと覚えています)は運動をした後の疲労回復にもとても効果があるので、スポーツをしている子どもにも食べてほしい野菜の一つです。
今回は、そんな「赤パプリカ」について、赤パプリカに含まれる栄養素とその働きや、1日に摂りたい量や、食べ過ぎは良くないのか?についてお話していきたいと思います。

赤パプリカに含まれる栄養素とその働きは?
赤パプリカには、主に「βカロテン」「ビタミンC」「カプサイシン」が含まれています。
それぞれの栄養素とその働きについて見ていきましょう!
「βカロテン」
βカロテンとは、緑黄色野菜に多く含まれている栄養素で赤色のもとになっている成分です。
またβ–カロテンは体内で必要な分だけビタミンAに変換され、体内の活性酸素を減らす抗酸化作用があります。
抗酸化作用で活性酸素を除去してくれるので、粘膜を丈夫にして免疫力を高める効果があります。

運動をすると活性酸素が発生し細胞を傷つけると体の働きが低下してしまうんです。これが「疲労」です。

つまり、その「疲労」のもととなる活性酸素を除去してくれるということは、βカロテン(ビタミンA)は疲労回復に効果があるということですね。
また、ビタミンAの効力によって常に新しい細胞に入れ替えたり修復できる事で、シミやニキビだけでなく多くの肌トラブルの予防や改善に繋がるんです。
「ビタミンC」
ビタミンCと言えば「レモン」などが思い浮かびますが、以外にもレモンよりもビタミンCが豊富な野菜です。
ビタミンCにもβカロテンと同じく、活性酸素を除去する抗酸化作用があります。
ビタミンCは、本来水溶性のビタミンで熱に弱い性質ですが、赤パプリカに含まれるビタミンCは繊維組織に守られているため、加熱しても損失しにくいという特徴があります。
さらに、油とともに摂取することでβ-カロテンの吸収率が高まるので、サラダだけでなくオリーブオイルで炒めるなど油と一緒に調理するのもおすすめです。
「カプサンチン」
赤い色素の成分であるカプサンチンが含まれています。
カプサンチンは、カロテン以上の強い抗酸化作用があり、善玉コレステロールを増やす働きがあり生活習慣病全般に効く成分として注目されています。
1日に摂りたい量は?食べ過ぎは良くない?
赤パプリカには、お話してきたβカロテン・ビタミンC・カプサンチン以外にもビタミンE、カリウム、食物繊維といった栄養素がたくさん含まれており積極的に摂りたい野菜です。
では、一体1日にどのくら食べたら良いの?と気になりますよね。
結論から申しますと、1日に1個くらいが適量です。
なぜかと言うと、赤パプリカには食物繊維も豊富に含まれているので食べすぎてしまうとお腹を下してしまう可能性があるんです。
適量ならば、便秘解消効果も期待できるのですが、効果が出すぎてしまっても良くないということですね、
同じく、赤パプリカに含まれているカプサンチンも、脂肪燃焼効果も期待できるのですが、食べ過ぎると胃腸を刺激してしまう恐れも…。
また、カリウムも利尿効果があるのでダイエットにも向いている野菜なのですが、摂りすぎてしまうと体を冷やしてしまう事もあります。
以上のことから1日1個程度をめやすにすると良いですよ♪
まとめ
いかがでしたでしょうか?
赤・黄色・オレンジと色鮮やかなパプリカ。
パプリカの中でも、緑黄色野菜でありビタミンが豊富な「赤パプリカ」。
赤パプリカにはビタミンA・C・Eが含まれていて、運動した後の疲労回復にもとても効果がある野菜です。
今回は、私もダイエットと健康のために毎日食べているビタミン豊富な「赤パプリカ」についてお話しました。
季節の変わり目は、風邪も引きやすいので赤パプリカを食べて疲れをとりましょう!
最後まで読んでいただきありがとうございました。
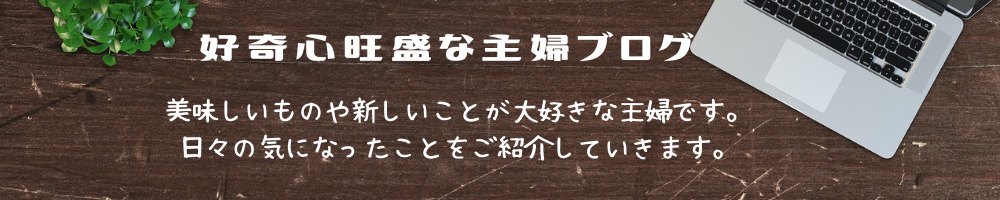



コメント